書籍内容の紹介
人財のブラッシュアップが企業と地域を元気にする
-
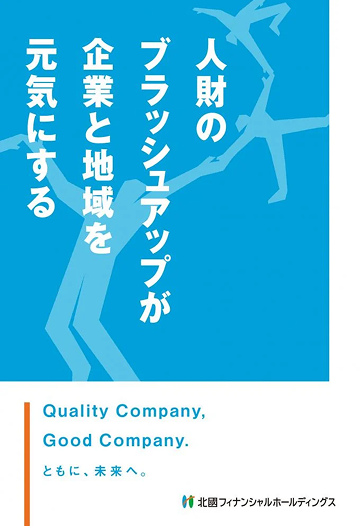
- 北國フィナンシャルグループが営業ノルマ廃止を契機に進めてきた組織・人事・文化改革の軌跡をまとめたものです。営業スタイルの転換、人事制度の刷新、リカレント教育の推進、地域企業との連携など、顧客本位の経営を実現するための挑戦と実践が、豊富な事例とともに描かれています。社員の自律性と対話を重視した企業文化の醸成を通じて、「良い会社」への道を探る取り組みが綴られています。
- 発刊:2022年
- 書籍のご購入はこちら
第1章:ノルマ廃止前の混乱
2015年に営業ノルマを廃止した際、社内外に大きな波紋が広がりました。社員の間では「目標がなくなるのでは」「評価はどうなるのか」といった不安が噴出し、顧客からも「銀行はもう営業しないのか」といった誤解が生まれました。背景には、かつての「ALL営業」運動の失敗があり、営業改革と人事制度改革を切り離して進めたことが混乱を招いたという反省があります。ノルマ廃止は単なる制度変更ではなく、コスト構造の見直しと人的・IT投資への再配分を可能にする戦略的な一手であり、営業現場の意識改革と組織全体の再設計が求められたのです。
第2章:組織文化改革への挑戦
昭和型の営業・評価・人事制度から脱却し、令和型の「顧客本位」な組織文化への転換が始まりました。従来の「売る営業」から「寄り添う営業」へとシフトする中で、営業部門の廃止やFDアドバイザリーの設立といった大胆な組織再編が行われました。評価制度も、結果重視からプロセス重視へと転換し、短期的な成果よりも顧客との長期的な信頼関係構築が重視されるようになりました。こうした変革は、単なる制度変更ではなく、社員一人ひとりの価値観や行動様式の変化を伴う「文化の変革」であり、継続的な対話とリーダーシップが不可欠でした。
第3章:人事制度改革とコミュニケーション
2022年3月に導入された「キャリア型」人事制度では、従来の年功序列的な賃金テーブルや退職金制度を廃止し、役割・成果に応じた報酬体系へと移行しました。評価は複数部署のリーダーによる多面的な視点で行われ、社員のキャリア自律性が重視されるようになりました。また、Microsoft Teamsやグループウェアを活用した情報共有が進み、心理的安全性を確保した対話文化が根付きつつあります。社員が自由に意見を述べられる環境づくりが、組織の柔軟性と創造性を高めています。
第4章:リカレント教育とコラボレーション制度
「100年人生」時代に対応するため、社員の継続的な学びを支援するリカレント教育制度が整備されました。MBA取得支援では、受講料の3分の2(約200万円)を会社が負担し、すでに30名が受講。社内副業制度「コラボレーション制度」では、部署を越えたプロジェクト参加が可能となり、社員の挑戦と成長を後押ししています。これにより、社員は自らのキャリアを主体的に設計し、専門性を高めながら組織に新たな価値をもたらすことが期待されています。
第5章:地域企業への人材育成コンサルティング事例
地元企業との連携による人材育成支援が進められています。若手社員へのマナー研修や問題解決力向上、リーダー層への財務計画研修など、企業の課題に応じたオーダーメイド型の支援が実施されています。評価制度の見直しや管理職研修など、実践的な取り組みが成果を上げており、コンサルティングの現場では、社員の声を反映した制度設計や、継続的なアフターケアによる定着支援が行われています。こうした取り組みは、地域企業の持続的成長と人材定着に大きく貢献しています。
第6章:Quality Company & Good Companyを目指して
「量」よりも「質」を重視する経営方針のもと、地域社会への貢献と社員の成長を両立させる企業文化が育まれています。哲学やリベラルアーツの知識をビジネスに活かし、対話と協働によるイノベーション創出を重視。2008年に制定された「20の行動原則」は、社員の行動指針として定期的に見直され、時代に即した価値観を反映しています。ヘーゲルの「アウフヘーベン」の概念を引用し、対立する価値観を統合しながら高次の解決を目指す姿勢が、組織の持続的成長を支えています



